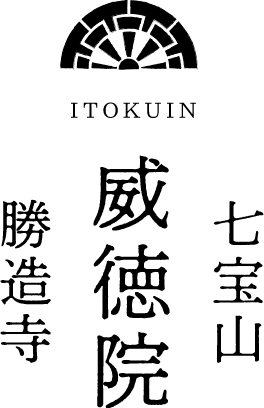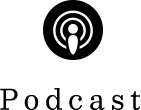(三月法話) お彼岸
2月があっという間に終わり今日から3月です。「暑さ寒さも彼岸まで。」寒い冬が過ぎると動植物が待ちに待った春が訪れます。「春の彼岸」は春分の日を中心に7日間です。今年は3月17日が彼岸の入りで、20日が中日、23日が彼岸の明けです。
彼岸はインドの言葉(梵語)では「パーラミター(波羅蜜多)」で「至彼岸」と漢訳され、河を渡って安楽の世界へ赴(おもむ)くことです。
彼岸の期間には、お墓参りをしての先祖供養は欠かすことができませんが、お彼岸のお供えといえば、もち米と餡子(あんこ)で作ったお餅です。
老師から『春の彼岸にお供えするお餅は、漉し餡(こしあん)を使って牡丹の花のように作るので「牡丹餅(ぼたもち)」というのだ。一方、秋の彼岸には萩の花に似せて粒餡(つぶあん)で作るので「お萩餅」と呼ぶのだ』と聞いたことを思い出します。同じ食べ物でも季節によって呼び名が異なるのは、わが国文化の奥深さゆえかもしれません。
彼岸にはお墓やお仏壇にお参りして亡き人とのつながりを感じ、ご先祖さまに支えられて今を生きているわたしたちがあることを見つめ直す時でもあります。今のわたしたちの存在は、無数の名も知らぬご先祖さまが、それぞれの人生を生き抜いてつなげてきた絆によるものです。季節が移り変わりながらもつながっているように、わたしたちも無数のご先祖さまとつながっているのです。
春の彼岸には、お仏壇に「牡丹餅」をお供えし、家族そろってお参りしましょう。日常生活は慌ただしく過ぎて行きがちですが、この時ばかりは日ごろ忘れているご先祖さまに感謝する機会としたいものです。