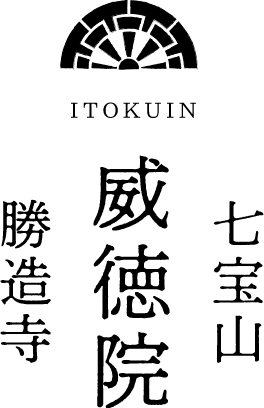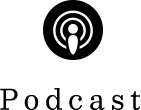真言宗について

真言宗は弘法大師空海によって開かれ、密教の教えを説きます。説法主は大日如来です。この大日如来だけが完全無欠な仏で、宇宙の真理そのものを意味しています。弘法大師空海は、宇宙に存在するものはすべて大日如来の表れであり、そのものにしかない、かけがいのない価値を持っているものと説きます。
即身成仏
真言宗では私たちの身体に印契(いんげい)を結び、口に真言を唱え、心を禅定にして仏の三密(身口意)と一体となることによって、父母から授かったこの肉体のまま成仏(悟りを開くこと)することが出来るのです。
悟りの世界を象徴で表現
真言宗の教えは隠密で言葉や文字では相手に伝えることはできないが、図画の形など象徴を持ってすれば伝えることが出来ると説きます。だから、絵画や工芸など芸術文化を大切にするのです。
弘法大師
空海について

弘法大師空海は、香川県仲多度郡(現善通寺)に拠点を置いていた佐伯氏の出身です。奈良時代終わりごろから平安時代の初めころに活躍した思想家で、真言宗の開祖です。幼名を真魚(まお)といい、遣唐船で中国・唐へ行き恵果和尚(けいかかしょう)から密教(秘密仏教)を伝授され、わが国へ最初に密教を伝えた方です。
この密教は顕教に対する言葉です。顕教(けんぎょう)はわが国に伝わった言葉や文字で示された釈尊の教えで、具体的に説明すればその働きは、表面に積もった塵を払い見た目を美しくすることができますが、一方、密教の働きは庫(くら)を開いて中に秘蔵されている宝を見つけ出すことができる教えです。
また、顕教は三劫(さんごう)という無限に近い長い間の成仏への修行を必要としますが、密教は父母から授かったこの肉体のままで成仏(悟りを開くこと)することができるという即身成仏を説きます。
弘法大師は「私の目的は、国の平和と人びとの幸福(しあわせ)を願うことだ」と述べているように、生涯をかけて人びとの幸福を願われた人でした。だから、弘法大師空海は人びとが幸福になるための方法として新しい文化や、まだわが国に伝えられていない優れた技術、例えば満濃池の修築で用いたアーチ式や余水吐(よすいはき)の技術などを唐から持ち帰ったのです。
創建

威徳院は平安時代の821年(弘仁12年)に弘法大師空海により創建されました。中興の祖は一一四六年(久安二年)に住職となった浄賢といわれますが、その後栄枯盛衰。
安土桃山時代になると生駒親正が入府し真言宗寺院を保護して「讃岐十五箇院」を定めた時に、その一つに数えられました。さらに生駒一正の書状が伝存するように生駒一正の帰依を受けて隆盛をみます。
江戸時代初期になると「讃岐六院家」(虚空蔵院与田寺・宝蔵院極楽寺・明王院道隆寺・誕生院善通寺・威徳院勝造寺・地蔵院萩原寺)に数えられ、讃岐の中心寺院として真言の教えを伝え、子弟教育に尽力しました。
江戸時代後期には「西讃五箇院」(持宝院本山寺・延命院勝楽寺・伊舎那院如意輪寺・覚城院不動護国寺・威徳院勝造寺)として末寺に関する寺務を行いました。1741年(寛保元年)に住職となった周峯は、境内整備に着手し伽藍(修行の場)と本坊(僧侶の住居)を分けて、丸亀藩より寄進を得て丸山台地に本堂を建て、大師堂・毘沙門堂・八幡社・鐘楼などを整備しました。
1998年(平成10年)に始まった平成の大修理で本堂を250年ぶりに元の場所に新築し、丸山台地の旧本堂を奥の院奥殿として整備し現在に至ります。
ご本尊
ご本尊は秘仏十一面観音菩薩で右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に水瓶を持つ、奈良県の真言宗豊山派の総本山・長谷寺の本尊と同形のもので、脇侍(わきじ)には、難陀龍王(なんだりゅうおう)と雨宝童子(うほうどうじ)を従えています。威徳院文書「縁起集」には「世にまれな霊仏にして長谷寺の本尊と同体一身の尊像である」と書かれており、長谷式観音菩薩として信仰されてきました。
由来
弘法大師空海が821年(弘仁12年)に満濃池を修築するために讃岐に帰られたとき、この地に草房(草ぶきの家)があったので、しばらく留まり修禅されたのを威徳院の開基としています。
あゆみ

| 821年(弘仁12年) | 弘法大師空海により創建 |
|---|---|
| 1146年(久安2年) | 浄賢法印大和尚が住職となり威徳院を復興 |
| 1587年(天正15年) | 生駒親正が定めた「讃岐十五箇院」の一つに選ばれます |
| 1611年(慶長16年) | 高松に19か寺を集めた論議興行(善通寺文書)に威徳院の寺名が確認できます |
| 1642年(寛永19年) | 寺領高20石 |
| 1653年(承応2年) | 『四国辺路日記』で、讃岐の中心的な寺として六院家の一つに威徳院が数えられました |
| 1665年(寛文5年) | 威徳院において、讃岐国中の住職を集めて宗門改めが行われました |
| 1699年(元禄12年) | 寺領高43石7斗3合。最終的には150石となりました |
| 1725年(享保10年) | 持宝院(本山寺)の住職・素光が威徳院に転住 |
| 1741年(寛保元年) | 持宝院(本山寺)の住職・周峯が威徳院に転住 |
| 1742年(寛保2年) | 周峯が京極家から丸山台地の永代免許の許可を得て境内整備に着手 |
| 1751年(宝暦元年) | 本堂を新築 |
| 1799年(寛政11年) | 毘沙門堂を建立 |
| 1818年(文化15年) | 八幡社、鐘楼を建立 |
| 1820年(文政3年) | 持宝院(本山寺)の住職・本具が威徳院に転住 |
| 1868年(明治元年) | 勝間村(現香川県三豊市)の13宮社の御神体を威徳院八幡社に統合 |
| 1998年(平成10年) | 平成大修理。本堂を250年ぶりに元の場所に新築し、丸山台地の旧本堂を奥の院奥殿として整備 |

住職について さかた 坂田 知應 ちおう 俗名 知己 ともき
1947年(昭和22年)香川県三豊市高瀬町生まれ。
高野山大学大学院修士課程修了。高野山大学で密教学の第一人者であった松長有慶先生に師事し、密教を学ぶ。大学院修了後、奈良市・元興寺文化財研究所研究員として仏教民俗学や仏教美術を研究するなど密教学を様々な面から研究。1980年(昭和55年)に威徳院28世住職に就任。
弘法大師空海の生涯やみ教えをやさしく説く講座「威徳院いろは塾」や『坂田和尚の紙説法』などを通して幸福に生き抜く教えを説いています。